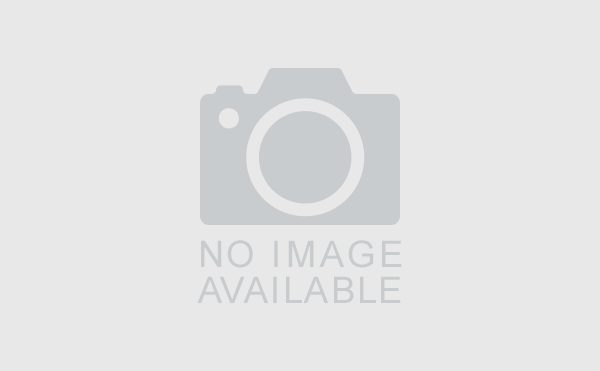「3m競走」から考える、子どもへの向き合い方
———-
こんにちは!
群馬県高崎の塾『学習塾ACT』の塾長 斎藤です!
当塾は小学生(5・6年生)・中学生・高校生を対象とした個別指導の塾です。
このブログでは、高崎市の学習塾『学習塾ACT』が、どのような塾かをご紹介いたします。
さて、本日は「3m競走」から考える、子どもへの向き合い方についてのお話です。
これから紹介する文章は、今から15年以上前に、ある中学校の先生が書かれたものです。
たまたま生徒が持っていたプリントを読ませてもらったのですが、心を揺さぶられる内容で、私は今でもそのコピーを大切に保管しています。
運動会の一場面を描いた短い文章です。
けれど、読み終えたときには「生きること」や「向き合うこと」の意味を深く考えさせられました。
以下に、その全文をご紹介します(筆者名は伏せさせていただきます)。
3m競走
「よーい、ドン」――威勢のよい合図で、その競技は始まった。
「がんばれ、がんばれ」の大声援が、周囲からわき起こった。
しかし、いつになってもランナーはスタートしなかった。―― ここは、とある養護学校。肢体不自由児のための学校である。
その運動会のプログラムには、50m走、30m走、10m走などの競技があった。
まず、比較的軽度の生徒は50mをチョチチョと走った。
次に、30mの生徒はヨロヨロと歩いてゴールした。
ここまでは「彼らなりに精一杯頑張っているのだなあ」ということで、観客席から大きな拍手もわいていたし、私も普通の気持ちで見ていられた。
しかし、重度の生徒が10m先のゴールを目指して這いはじめた時は、「自分の限界に挑戦する」などという言葉では言い尽くせないものを感じていた。
そして、3m競走の出場者が一輪車のようなものに乗せられて登場した時は、あきらかに空気がはりつめていた。
いったい彼らはどうやってゴールまでたどり着くのであろうか。
3m、たった3mの競走なのであるが、それが彼らにとってはとてつもなく長い距離なのである。
彼らはいつになってもスタートしなかった。
しばらくして、一人の生徒がゴロリと寝返りを打った。
続いて、他の生徒も必死の形相で寝返りを打ちはじめた。
しかし、筋ジストロフィーという筋肉に力が入らない病気の彼らにとっては、思うように手足が動かないので、寝返りを打つことさえたいへんなことである。
1分、2分と時間がたっていく。それでも、先生方は誰も助けようとはしない。
観客も、最初は力の限り応援していたが、次第にシーンと静まりかえって、この成り行きを見つめていた。
ようやく最後のランナーがゴールインした時は、大歓声と嵐のような拍手がわき起こったのは言うまでもない。
そして私は、いつの間にかボロボロと大粒の涙をこぼしている自分に気がついた。
善感の自分の生活を反省するとともに、能力がありながらサボっている多くの生徒たちのことを思って泣けてしまったのである。
勉強を精一杯しているわけでもないのに、「成績が上がらない」と嘆いている人。
他人と同じだけの練習しかしないのに、「レギュラーになれない」といじけている人。
「面倒くさいから」と、ほとんど掃除をやらない人。
その他「疲れるから」とか、「面白くないから」とか言い訳をして、何もしたがらない人…。
肢体不自由児の彼らは、何をしたくてもできないんだぞ。
それでも精一杯生きようとしているじゃないか。
君の目標は何m? そして、今、君は、全力を出しきって生きているか?
私たちは、子どもにどう関わっているか?
今の子どもたちは、「やりたくない」「無理そう」「楽しくない」と感じた瞬間に、簡単に立ち止まれてしまう時代に生きています。
それを「本人の意思」として尊重する空気が強くなり、大人が踏み込むことが難しくなっているのも事実です。
私自身、塾で真剣に子どもと向き合った結果、「行きたくない」と言われたり、保護者の方からお叱りのご連絡をいただいた経験もあります。
けれど―― 大人が何も言わなくなってしまったら、誰が子どもを育てるのでしょうか。
最後に、保護者の皆さまへ
子どもがやりたがらないとき、私たちはその気持ちをただ受け入れるだけでよいのでしょうか。
「頑張らなくても大丈夫」と言い続けることが、本当にその子の将来につながるのでしょうか。
耳の痛いことでも、必要なことは伝える。
やりたくない理由を受け止めながらも、「それでも一歩踏み出そう」と背中を押す。
それが私たち大人の役割ではないでしょうか。 あなたは、どう感じましたか?